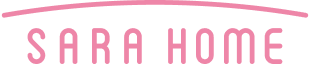後悔しないパッシブデザインの家づくり|建築設計のポイントと注意点

「夏は涼しく、冬は暖かい家にしたい」 これは、家づくりを考える多くの方に共通する願いではないでしょうか。そんな理想を、エアコンなどの設備に頼りすぎずに叶えるのが「パッシブデザイン」の住まいです。
パッシブデザインとは、太陽の光や熱、風といった「自然の力」を上手に取り入れ、快適な室内環境をつくる設計手法のこと。無理なく省エネを実現できることから、光熱費の高騰や環境意識の高まりを受け、導入を検討する方が増えています。
ただし、単に自然の力を取り入れれば良いというものではなく、設計のポイントを間違えると「思ったより快適にならなかった」と後悔につながる可能性も。この記事では、パッシブデザインの基本要素やメリット・デメリット、季節ごとの設計ポイントをわかりやすく解説します。理想の住まいを実現するために、ぜひ最後までご覧ください。
パッシブデザインとは何か

快適で省エネな暮らしを実現するための設計思想が、パッシブデザインです。住宅の性能や間取り、開口部の位置などを工夫し、自然エネルギーを最大限に活かすことを目的としています。
まずは、その基本的な考え方からみていきましょう。
パッシブデザインの基本概念
「パッシブ(Passive)」とは「受け身の」「受動的な」といった意味を持つ言葉です。その名の通り、機械的な冷暖房に「積極的(Active)」に頼るのではなく、自然の力を「受け身(Passive)」の姿勢で上手に取り入れ、心地よい室内環境をつくるという考え方を指します。
冬は太陽の光を取り込み、室内に蓄えた熱で暖かく過ごす。夏は庇(ひさし)や軒、植栽などで直射日光を遮り、風の通り道を設計して自然の涼しさを取り込む。こうした工夫がパッシブデザインの基本です。
自然のエネルギーをどう活かすかを設計段階で考えることで、快適さを保ちながら冷暖房に使うエネルギーを減らせます。結果として、光熱費の削減やCO2排出の抑制にもつながるのです。
アクティブデザイン・パッシブハウスとの違い
似た言葉に「アクティブデザイン」や「パッシブハウス」がありますが、目的や手法にははっきりとした違いがあります。
「アクティブデザイン」は、太陽光発電や省エネ設備を「積極的に利用」してエネルギー効率を高める方法です。一方、パッシブデザインは建物そのものの性能や形状でエネルギーをコントロールし、設備に頼りすぎない暮らしを目指します。
「パッシブハウス」はドイツで生まれた住宅性能基準で、断熱・気密の数値を厳格に定めたものですが、これが厳格な性能基準(認証)を指すのに対し、「パッシブデザイン」は、日本の地域の気候や四季の変化を踏まえた柔軟な設計「手法」や「思想」そのものを指すという違いがあります。
「パッシブデザイン」は、土地の条件に合わせた工夫を積み重ねることで、自然と共に心地よく暮らせる住まいをつくる考え方なのです。
パッシブデザイン設計の5大要素

パッシブデザインは、単に自然を活かすだけでは成立しません。建物の性能・形状・配置などを総合的に計画し、季節や時間帯によって変化する自然条件をコントロールする必要があります。
ここでは、その根幹をなす以下5つの設計要素について解説していきます。
①断熱計画
②日射遮蔽
③自然通風
④昼光活用
⑤日射熱活用
①断熱計画
断熱は、パッシブデザインの基盤です。外気の影響を受けにくくすることで、室内の温度を一定に保ち、冷暖房に頼りすぎない暮らしを可能にします。断熱性能を高めるには、壁・床・屋根・窓といった「外皮」全体のバランスが重要です。
また、断熱材の性能だけでなく、施工の精度も快適性を左右します。「気密性(すきまをなくすこと)」を確保することで、断熱材が持つ本来の性能を最大限に発揮させ、冬の暖気や夏の冷気が(すきま風として)逃げるのを防ぎます。
まず「魔法瓶(サーモボトル)」のような高性能な「土台」をつくることが、他の4要素を活かすための大前提となります。
②日射遮蔽(夏の対策)
「夏」の強い日差しをどれだけ防げるかは、快適さと省エネの両方に直結します。そこで役立つのが、庇(ひさし)やルーバー、軒、外付けブラインドなどの「日射遮蔽」です。
ポイントは、太陽高度が高い夏の時期に合わせて適切な庇の出幅を設けることで、室内に侵入する熱を効果的に遮ること。南面の大きな窓は、冬はメリットになりますが、夏は過剰な熱を室内に招くため、この「遮蔽」が不可欠です。また、落葉樹やすだれを組み合わせれば、季節の変化に合わせた柔軟な調整も可能です。
③自然通風(夏の対策)
「夏」に、風の通り道を設計に取り込むこともパッシブデザインの大切な要素です。窓をただ開ければ風が通り抜けるわけではないため、風の入口と出口の位置・高さ・向きを考慮しながら配置します。例えば、風上と風下に対角線上で窓を配置すると、効率的に風が抜けるようになります。
さらに、吹き抜けや階段室などの「縦の抜け」を利用すると、上昇気流によって空気が循環しやすくなります。こうした工夫により、エアコンに頼る時間を減らし、自然の風が流れる心地よい空間をつくれるのです。
④昼光活用(光の設計)
光の扱い方で、住まいの印象や快適さは変わります。パッシブデザインでは、純粋な「明るさ」をどう確保するかを設計段階で考えます。人工照明に頼りすぎず自然光で明るさを確保することで、省エネと心地よさを両立できるのです。
例えば、安定した光が得られる北側の窓(高窓)を設けたり、吹き抜けを通じて1階の奥まで光を届けたりすることで、日中の人工照明の使用を減らし、心地よい空間をつくります。 (※昼光活用は、夏の日差しを遮る「遮蔽(②)」や、冬の日差しを入れる「熱活用(⑤)」とは目的が異なる「明るさ」のための設計です)。
⑤日射熱活用
冬に暖かく過ごすための工夫が「日射熱活用」です。④の昼光活用が「明るさ」を目的とするのに対し、こちらは「熱(エネルギー)」を室内に取り込み、蓄えることを目的とします。具体的には、日照シミュレーションを活用し、太陽高度が低くなる冬に、室内の奥まで日射が届くよう窓の位置やサイズを計画します。
さらに、取り込んだ熱を逃がさないよう、コンクリート土間や室内の壁など、蓄熱性(熱を蓄える性質)の高い素材を組み合わせることで、日中の熱を夜までゆるやかに放出し、暖房負荷を減らします。 ①の断熱計画との組み合わせにより、冬の暖房費を抑えながら快適に過ごせる住まいが完成します。
パッシブデザイン住宅のメリット

パッシブデザインの家は、自然の力を味方につけて、心地よさと省エネを両立させる住まいです。
「冷暖房に頼りすぎず、家そのものが季節に寄り添ってくれる」、そんな暮らしは多くの人が理想とするものではないでしょうか。
ここでは、パッシブデザインがもたらす魅力を具体的に紹介します。
一年中快適な室内環境を保てる
「冬の朝、リビングに足を踏み入れても、床がひんやりしない」
「夏の夕暮れ、カーテン越しにやわらかな風が抜けて、エアコンをつけなくても涼しい」
こうした穏やかな室内環境をつくれるのが、パッシブデザインの家です。
断熱や日射コントロールなどの工夫により、外気の影響を受けにくく、家全体の温度差も少なくなります。これにより、冷房や暖房を強くかけなくても室温を一定に保ちやすいため、体にも家計にもやさしい、年間を通じた快適な暮らしが叶うのです。
光熱費を抑えられる
毎月の光熱費がぐっと減るのも、パッシブデザインのうれしいポイント。断熱性を高め、自然光や風を取り込むことで、冷暖房の使用を最小限にできます。冬は日射熱でぽかぽかと暖かく、夏は庇や風通しで自然に涼しさを維持。その結果として、電気代をはじめとする光熱費の負担を少なく抑えられます。
「少しの工夫で、こんなに違うんだ」と感じる人も少なくありません。光熱費の値上がりが続く中でも、エネルギーに頼りすぎない家なら今後も安心して暮らせますね。
健康的な生活を送れる
住まいの温度・湿度の安定は、家族の健康維持に直結します。パッシブデザインの住宅は、熱や光のバランスを整えることで、季節の変化に左右されにくい室内環境を実現。急な温度差によるヒートショックや、結露から生じるカビ・ダニの発生を抑えられます。
結露が減ることは、柱や土台といった構造躯体の腐食を防ぐことにもつながり、結果として家の寿命(資産価値)を守ることにもつながります。特に小さなお子様や高齢者のいる家庭では、家全体がほぼ一定の温度で保たれることが大きな安心につながるでしょう。
また、自然光を取り入れた明るい空間は、心の安定にも効果的です。日中は電気をつけなくても快適な明るさで過ごせるため、開放感が生まれ、気持ちも前向きになります。こうした自然のリズムに沿った暮らしが、心身ともに健やかな生活につながるのです。
エコで地球にやさしい暮らしができる
冷暖房の使用を減らし、電力やガスの消費を抑える暮らしは、地球への負担も軽くできます。
家族が快適に過ごしながら環境にも配慮する考え方こそ、パッシブデザインの根底にあるもの。
太陽の光や風といった身近な自然エネルギーを活用することが、CO2排出を抑え、環境負荷の削減につながるのです。
「自分たちの心地よさが、未来のやさしさにつながっていく」そんな家づくりこそ、これからの時代に求められる住まいのかたちといえるでしょう。
パッシブデザイン住宅のデメリットと対策
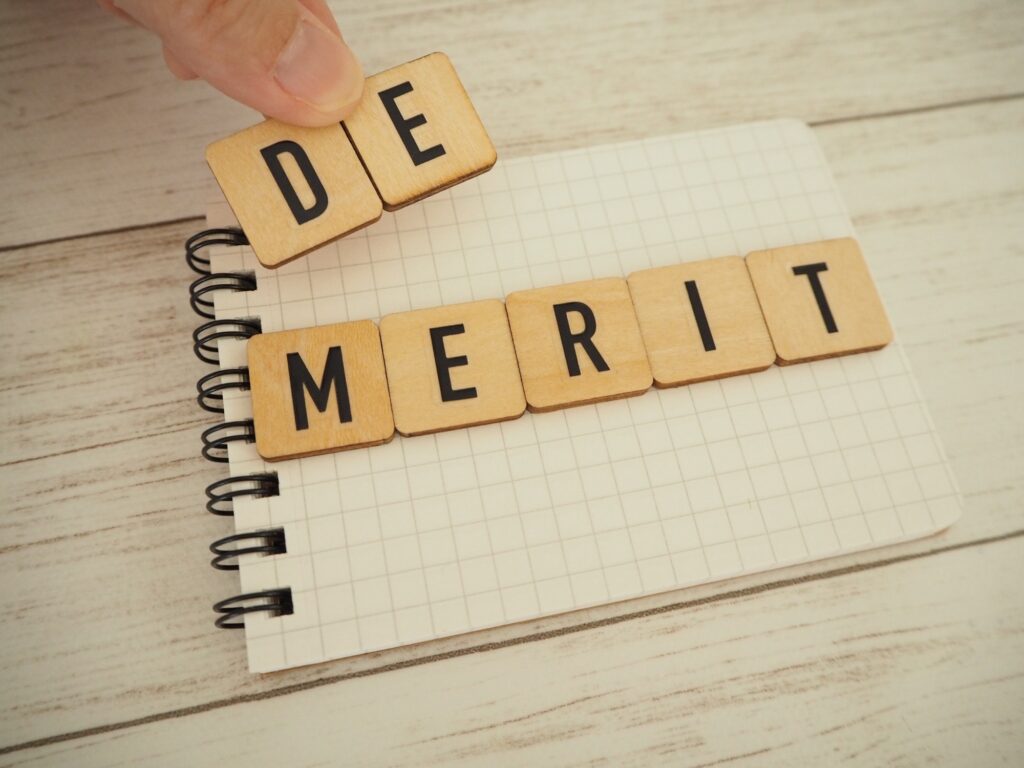
どんなに優れた設計手法でも、万能というわけではありません。パッシブデザインにも、コストや条件、設計上の制約といった注意点があります。ただし、それらを正しく理解し対策を講じれば、後悔のない家づくりができます。
ここでは、よく挙げられる4つのデメリットと解決のヒントを紹介します。
初期コストが高くなりやすい
断熱材のグレードアップや高性能サッシの採用など、性能を高めるための仕様を選ぶと、どうしても建築コストは上がりがちです。もちろん、光熱費など「長期的なコスト(ランニングコスト)」が削減できるため、トータルでの費用対効果は高いといえます。
その上で、初期コスト自体を抑えたい場合は、全てを高性能化するのではなく、「性能への影響が大きい部分にコストを集中させる」という優先順位づけが有効です。例えば「(日射熱を活用したい)南側の開口部は高性能な窓にする一方、(熱が逃げやすい)北面は窓を最小限にして壁の断熱性能を高める」など、メリハリをつけるのです。設計士のアドバイスを受けながら、性能とコストのバランスを見極めましょう。
設計・施工できる会社が限られる
パッシブデザイン住宅は、一般的な「高気密・高断熱住宅」とは一線を画す存在です。敷地条件・日射角度・風向きなど、地域特性に合わせた計算と設計ノウハウが求められるため、どの会社でも同じようにプランニングできるわけではありません。そのため、対応できる設計・施工会社は限られるのが現実です。
依頼先を探すときは、パッシブデザインの実績が豊富かどうかを確認しましょう。気候や敷地条件を読み取る設計力があるか、施工精度をどこまで担保しているかは、見学会や施工事例で確かめるのが確実です。また、設計士が自社に在籍しているかどうかも重要なポイント。外注ではなく一貫体制で取り組む会社なら、設計意図が現場までしっかり反映されやすく、性能面でも安心です。
立地条件に左右される
パッシブデザインは、太陽や風など自然のエネルギーを活かす設計。そのため、周囲に高い建物があったり敷地が狭かったりすると、十分な日射や通風を得られない場合があります。
【既に土地をお持ちの場合】
こうした制約も、設計の工夫である程度補うことが可能です。例えば、高窓(ハイサイドライト)や吹き抜けで安定した北側からの採光(昼光活用)を確保したり、風の通りをシミュレーションして最適な換気ルートを設けたりと、「できること」を最大化する方法が考えられます。
【これから土地をお探しの場合】
もちろん、理想は土地選びの段階からパッシブデザインを考慮することです。 これから土地選びを始める方は、ぜひ設計士や経験、知識が豊富な住宅会社の担当者と一緒に敷地を見て回りましょう。プロならではのアドバイスがもらえ、理想に近い家づくりが叶います。
設計の自由度が低くなる場合がある
パッシブデザインでは、日射や風の流れを考慮するため、窓の位置や間取りの自由度が制限されることがあります。例えば、「この位置に大きな窓を付けたい」「家の形をもっと個性的にしたい」といった希望が、性能面の理由で難しくなるケースも。
しかし、「自由度が下がる=デザイン性が損なわれる」とは限りません。光や風の入り方を考えた設計は、むしろ「理由のある美しさ」を生み出します。性能を担保しつつ、施主の希望するデザインにどう近づけるかは、設計士の腕の見せ所でもあります。
大切なのは、「デザインか、性能か」の二択で考えるのではなく、両者を高いレベルで両立させる方法を、設計士とことん話し合うこと。素材や窓の形状、陰影のつくり方など、工夫次第で意匠性と性能の両立は十分に可能です。
後悔しないパッシブデザイン住宅の設計ポイント

パッシブデザインの本質は、自然と折り合いながら快適さをつくること。冬と夏、それぞれの季節で「光・風・熱」の扱い方を変えることで、一年を通して無理のない心地よさが生まれます。
冬季の設計ポイント
冬の住まいづくりでは、太陽のぬくもりをいかに室内に取り込むかがポイントです。太陽高度が低い冬に、南面の窓から室内の奥まで日射が届くよう適切に配置すれば、日中の室温を自然に高められます。 取り込んだ熱を逃がさないためには、断熱性と気密性の確保が欠かせません。
さらに床や壁に蓄熱性のある素材を取り入れると、昼間に蓄えた熱が夕方までゆるやかに残り、暖房に頼りすぎずに過ごせます。また、暖気は天井付近にたまりやすいため、シーリングファンで空気を循環させると、室内の温度差を抑えられます。
寒さの厳しい冬本番でも、足元からふんわりと暖かさを感じられる空間をつくることが理想です。
夏季の設計ポイント
夏の住まいづくりでは、「熱を入れずに(日射遮蔽)」「風を通す(自然通風)」ことが快適さのポイントになります。日射が強く差し込む時期は、庇(ひさし)や軒、外付けルーバーなどを使い、室内に侵入する熱(直射日光)を遮ります。角度や出幅を設計段階で調整することで、不要な熱は防ぎつつも、安定した明るさ(昼光活用)を確保できます。
特に熱を受けやすい屋根は、断熱の強化や、太陽光パネルを設置して日陰をつくる(二重屋根化)といった工夫が効果的です。さらに、風通しを意識した開口計画も欠かせません。風上と風下の窓を対角に配置したり、高窓を設けて上昇した熱気を逃がしたりすると、室内に自然な風の流れが生まれます。
夕方、カーテン越しに風が抜けていくとき、自然の力で整えられた涼しさを実感できるでしょう。
【施工事例】パッシブデザイン住宅の成功例を紹介
「サラホーム」桜建築事務所では、敷地条件やご家族の暮らし方に合わせて、自然の力を最大限に活かす設計を行っています。
ここでは、パッシブデザインの考え方を取り入れた3つの事例をご紹介します。
ウッドデッキで外とつながる家

川沿いの緑豊かな敷地を活かした事例です。駐車スペースの上に広いウッドデッキを設け、LDKとゆるやかにつながる空間を計画しました。このウッドデッキは、LDKの大きな窓に対する「庇(ひさし)」としても機能し、夏の強い日差しを遮る役割(日射遮蔽)を果たしています。

外と中の一体感(開放感)と、高い断熱・気密性能、そして川沿いの立地を活かした「風通し(自然通風)」が組み合わさり、快適な住まいになりました。

▷施工事例の詳細はこちら
光あふれる吹き抜けと坪庭のある家

南向きの立地を活かした事例です。吹き抜けと高窓から光と熱をたっぷり取り込み、家中が明るく暖かい空間(昼光活用・日射熱活用)に仕上げました。この大空間に取り込んだ「自然の熱」を無駄にしないよう、シーリングファンで空気を循環。冬は上部にたまる暖かい空気を居住スペースへ戻すことで、最小限の暖房で快適に過ごせるよう工夫しています。

リビング脇には水槽、浴室の外には坪庭を設け、室内でも自然の癒しを感じられます。
大空間でも断熱・気密性をしっかり確保し、一年を通して快適に過ごせる住まいになりました。

▷施工事例の詳細はこちら
スキップフロアで光と広がりを生んだ家

開口を抑えた外観ながら、室内の明るさと開放感を実現した事例です。スキップフロアと吹き抜けを組み合わせ、立体的に光と風の通り道を計画しました。道路側からのプライバシーを守るために最小限の窓に抑えつつも、十分な採光(昼光活用)と通風(自然通風)を確保しています。

高性能な断熱・気密性と組み合わせることで、エアコン1台でも一年中快適に暮らせる住まいになりました。

▷施工事例の詳細はこちら
まとめ|厚木・海老名・町田でパッシブデザイン住宅を建てるなら「サラホーム」桜建築事務所へ
パッシブデザインは、自然の光・風・熱を建物の設計でコントロールし、快適性と省エネ性を両立させる考え方です。家の断熱と自然の風、太陽の光と熱を総合的に計画することで、冷暖房に頼らず、年間を通して安定した室内環境をつくります。光熱費の削減や健康面でのメリットも大きく、暮らしの質を高める手法として、今後さらに注目されていくでしょう。
厚木・海老名・町田エリアでパッシブデザイン住宅をご検討中なら、「サラホーム」桜建築事務所にご相談ください。この記事で解説したように、パッシブデザインは「5つの要素」を土地の条件に合わせて緻密に計画し、「コスト」や「デザイン」とのバランスも取る必要がある、専門知識と設計力が求められる家づくりです。
「自分たちの土地で本当に効果が出るか不安」「デザインと性能をどう両立させればいいかわからない」など、「後悔しない」ためにクリアすべき様々な課題に対しても、パッシブデザインに精通した建築士が、ご家族のライフスタイルに合わせた最適なプランをご提案します。
――――――
監修者:髙橋 康征(たかはし やすゆき)
一級建築士/一級土木施工管理技士/CASBEE建築・戸建評価員/インテリアコーディネーター

日本大学生産工学研究科建築工学専攻修士課程を修了し、一級建築士として数多くのプロジェクトを手掛ける。家業の土木建設会社にて宅地造成・エクステリア施工業務を経て、桜建築事務所に入社。住宅分野に限らない幅広い知識による提案や固定観念に囚われない設計が好評を得ている。「ジャーブネット全国住宅デザインコンテスト グランプリ受賞」「2013年2022年2023年2024年LIXIL全国メンバーズコンテスト 地域最優秀賞受賞」など、住宅デザインコンテスト受賞実績を多数保有。