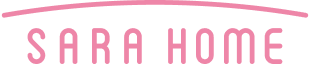【徹底解説】高性能住宅とは?メリット・デメリット、基準、失敗しない選び方

近年、「高性能住宅」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、具体的にどのような住宅を指すのか、どのようなメリット・デメリットがあるのか、そしてどんな点に注意して選べば良いのか、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、高性能住宅の基本から知っておくべき重要なポイントまでを分かりやすく紹介します。新築購入や注文住宅の計画など、これから家づくりをご検討の方はぜひ参考にしてください。
高性能住宅の特徴と重要な5つの要素

高性能住宅の基準や選ぶ際のポイントを理解するためには、まずその特徴となる5つの要素を押さえておくことが大切です。ここでは、それぞれの要素について分かりやすく解説していきます。
要素①【断熱性】
断熱性とは、住宅の壁、屋根、床、窓などから熱が逃げたり侵入したりするのを防ぐ性能です。
高い断熱性を備えた住宅では、冬は外の冷気をしっかり遮り、室内の暖かさを逃しません。また、夏は外からの熱気の侵入を防ぎ、家の中の涼しさを長く保てるのが特徴です。
断熱性能を客観的に示す指標に「UA値(外皮平均熱貫流率)」があります。これは、住宅の内部から外部へどれだけの熱が逃げやすいかを示す数値で、数値が小さいほど断熱性能が高いことを意味します。
地域によって求められる基準値は異なりますが、高性能住宅ではこのUA値を国の定める基準よりもさらに低い数値に設定することが一般的です。
要素②【気密性】
気密性とは、住宅にどれだけ隙間がないかを示す性能です。
気密性が低いと、高性能な断熱材を入れても隙間から熱が逃げたり、外気が侵入したりして、断熱性能が十分に発揮されません。そのため高気密住宅では、壁や床、天井などの接合部や窓の周りから隙間風が入ってこないように、徹底した気密処理が行われます。
気密性能を客観的に示す指標が「C値(相当隙間面積)」です。これは、住宅全体の隙間の面積を延床面積で割った数値で、数値が小さいほど気密性能が高いことを意味します。
C値は実際に専門の測定器を使って検査されるため、気密性における施工品質を実測値で確認できます。高性能住宅では、C値が0.5㎠/㎡以下であることが望ましいとされています。
要素③【耐震性】
地震大国である日本では、住宅の耐震性は非常に重要な要素です。
高性能住宅は、地震が発生した際に建物が倒壊したり、大きな損傷を受けたりすることを防ぐための強固な構造を備えています。現行の建築基準法に適合するだけでなく、さらに上位の耐震性を確保することで、より安全性の高い住まいを実現できるのです。
住宅の耐震性能をあらわす指標に「耐震等級」があり、3段階のレベルで評価されます。
・耐震等級1
建築基準法で定められた最低限の耐震性能。数百年に一度発生する大規模な地震に対しても倒壊・崩壊しないレベル。
・耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の耐震性能。学校や病院などの公共施設と同等のレベル。
・耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の耐震性能。災害時の救護活動の拠点となる警察署や消防署と同等のレベル。
高性能住宅では、家族の命と財産を守るため、最高等級である耐震等級3の取得を推奨しています。
要素④【耐久性・劣化対策】
住宅は一度建てたら終わりではなく、長く安心して住み続けるためには、時間とともに発生する劣化への対策が不可欠です。
高性能住宅は、構造材の腐朽やシロアリ被害、雨水の侵入などによる建物の劣化を防ぐための工夫が随所に施されています。これにより、住宅の寿命を延ばし、将来的なメンテナンス費用を抑えることにもつながります。
具体的な劣化対策としては、床下の湿気を防ぎ木材の腐朽やシロアリの発生を抑制する「基礎の高さや換気」、壁体内の湿気を排出し結露を防ぐ「外壁通気工法」、紫外線や雨風に強い「耐久性の高い建材の採用」、シロアリの侵入を防ぐ「防蟻処理」などが挙げられます。
要素⑤【省エネ性】
高性能住宅は、高い断熱性や気密性によって冷暖房の効率を大幅に向上させます。これにより、使用するエネルギー量を削減し、地球環境への負荷を減らすとともに、日々の光熱費を大幅に削減できるという大きなメリットが期待できます。
さらに、太陽光発電システムや高効率な給湯器などの導入により、より一層の省エネ化を図ることも可能です。
住宅の省エネ性能は「一次エネルギー消費量等級」という指標で評価されます。これは、冷暖房、換気、給湯、照明などのエネルギー消費量を総合的に評価するもので、等級の数字が大きいほど省エネ性能が高いことを意味します。
最高等級である等級6や等級7を取得すれば、年間を通じて光熱費の大幅な削減が期待できるでしょう。
高性能住宅のメリット

高性能住宅には、日々の快適さだけでなく、経済面や健康・安全面においても、一般的な住宅では得られないさまざまなメリットがあります。ここでは、具体的な利点を分かりやすくまとめて紹介します。
1年中快適な室温を保てる
高性能住宅の大きな魅力のひとつは、一年を通して室内の温度が安定しやすいことです。高い断熱性と気密性によって、外気温の影響を最小限に抑え、家のどこにいても大きな温度差を感じにくくなります。
冬はリビングだけでなく廊下やトイレ、脱衣所まで暖かさが行き届き、夏場もエアコン一台で効率的に涼しさを保つことが可能です。帰宅時の不快な「寒さ」や「暑さ」に悩まされることも減るでしょう。
光熱費を削減できる
高性能住宅は冷暖房効率が非常に高いため、必要なエネルギーを少なく抑えられます。
高い断熱性と気密性により、暖めた空気や冷やした空気が外に逃げにくく、エアコンの稼働も最小限で済みます。その結果、日々の光熱費が大きく下がり、一般的な住宅と比較すると年間で数万円から十数万円の節約が期待できるのです。
初期建築費用は多少高くなる傾向がありますが、長期的にはランニングコストが抑えられるため、トータルで見れば家計の負担を軽減できます。毎月の光熱費に悩むことなく、安心して生活を続けられるのも大きな魅力です。
健康的な暮らしを送れる
高性能住宅は快適なだけでなく、健康的な暮らしを後押しします。
高気密・高断熱の構造に加えて計画換気システムを備えることで、家の中は常に新鮮な空気が循環。結露やカビの発生が抑えられ、アレルギーやぜんそくなどの健康リスクが減少します。
窓を開けての換気もほとんど不要になるため、花粉やハウスダストの侵入も防ぎやすく、季節を問わず快適で清潔な空気環境を実現できます。
さらに家中の温度差が少なくなるため、冬場に起こりやすい「ヒートショック」のリスクを軽減できるメリットも。特に高齢者や小さなお子様がいるご家庭には、高い安心感を得られる住まいとなるでしょう。
災害に強く、修繕費も安く抑えられる
地震や台風など、自然災害が多い日本の住まいには、強さと安心が欠かせません。高性能住宅は耐震性や耐久性、劣化対策がしっかり施されているため、万が一の災害にも強く、大切な家族や財産をしっかり守ります。耐久性の高い外壁や屋根材の使用のほか、防蟻処理なども徹底されており、一般的な住宅よりもメンテナンスサイクルが長くなるため、大規模な修繕の頻度やコストが抑えられるのもメリットです。
定期的な点検や適切なメンテナンスを続けていけば、何十年経っても安心して住み続けられます。災害リスクを少しでも減らし、長く快適に暮らしたい方と考える方にぴったりの住まいといえるでしょう。
家が長持ちし、資産価値を維持できる
高品質な構造と明確な性能基準を備えた高性能住宅は、時が経ってもその価値を保ちやすいのが特徴です。
優れた断熱性や耐震性、省エネ性能など第三者機関による評価があることで、将来売却を考える際も買い手へのアピールポイントとなります。
築年数が経っても設備や性能が健全であれば、資産価値の下落を抑えられ、場合によっては高値での売却が期待できることも。転勤やライフスタイルの変化などで住み替えを検討する際も、安心して次のステップに進めるでしょう。
補助金や税制優遇を受けられる
国や地方自治体は、高性能住宅の普及を推進しており、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や長期優良住宅など、一定の基準を満たす住宅に対してさまざまな補助金制度や税制優遇措置を設けています。
高性能住宅は建築費用の高さで購入を躊躇する方も少なくありませんが、こうした制度を活用すれば数十万円から数百万円もの補助金や税制優遇を受けられるため、費用負担を大幅に減らすことも可能です。
適用される条件や期間は制度によって異なるため、申請検討時には最新の情報をチェックし、住宅会社などへ早めに相談しましょう。
高性能住宅のデメリットと注意点
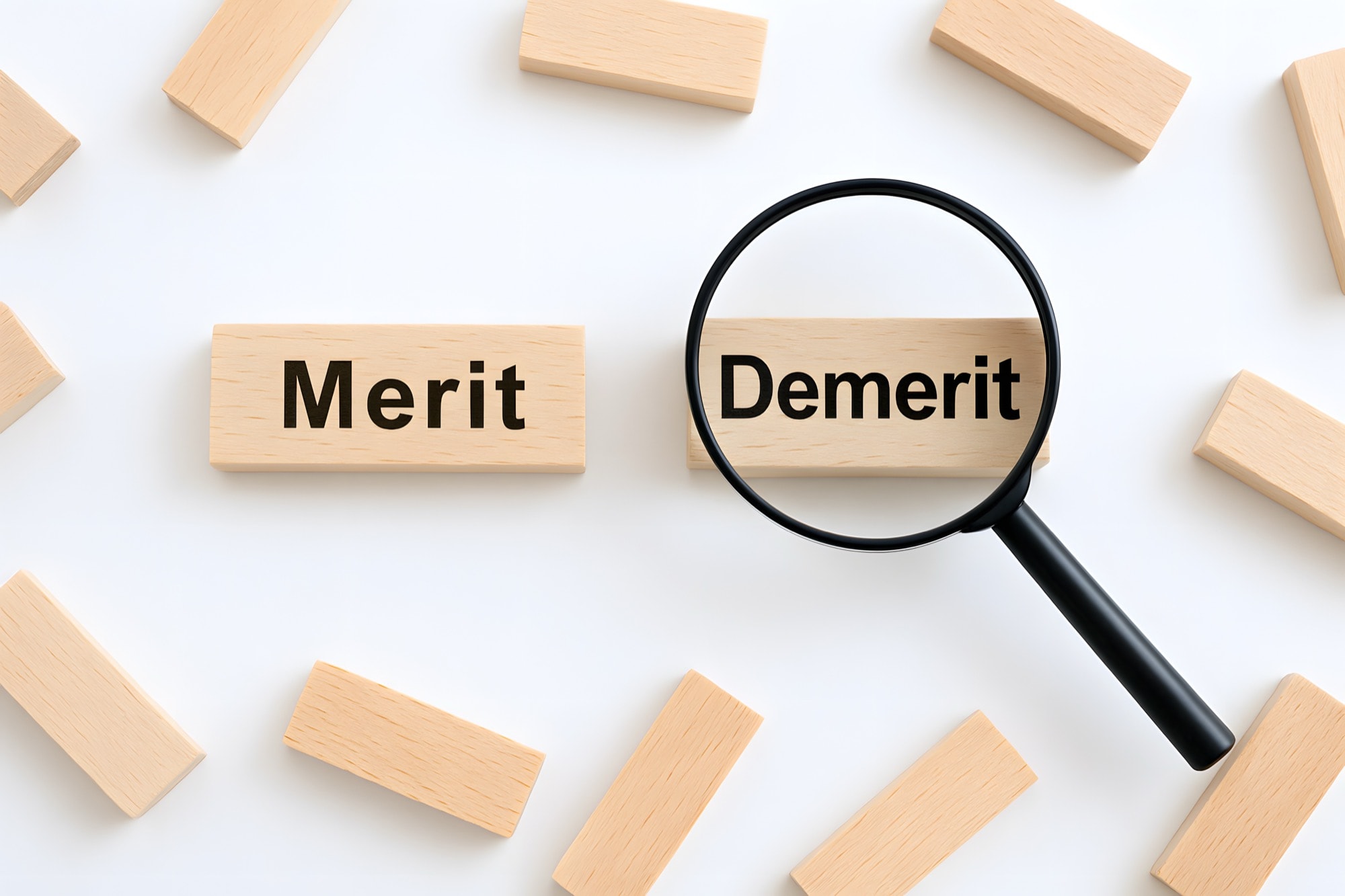
高性能住宅には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、後悔のない家づくりにつなげましょう。
建築費用が高くなりやすい
高性能住宅は、一般的な住宅と比較して建築費用が高くなる傾向があります。これは、高品質な断熱材やサッシ、換気システムなどの高性能建材を使用し、高い施工精度を維持するための丁寧な工事が必要になるからです。
しかし高断熱住宅は、光熱費やメンテナンス費用が安く済むため、長期的に見ればコストパフォーマンスの良い住まいといえます。太陽光発電などを活用すれば、初期投資を回収できる可能性も十分にあります。「健康リスクの防止」「資産価値の維持」といった観点からも、経済的なメリットは大きいといえるでしょう。
目先の費用だけでなく、ランニングコストや将来的な価値も含めて、総合的にコストパフォーマンスを判断することが大切です。無理のない資金計画を立て、納得のいく形で高性能住宅の建築を進めましょう。
換気・採光に工夫が必要になる
高性能住宅は気密性が高いため、自然換気だけでは不十分です。計画的な換気システムの導入が欠かせません。また、高気密・高断熱であるがゆえに、窓の配置や大きさによっては、室内に熱がこもりやすくなったり、逆に日差しが入りにくくなったりする可能性があります。
これらの課題は、設計段階での工夫で解決できます。例えば、熱交換型換気システムで効率的な換気を促したり、深い軒の設置やLow-E複層ガラスの採用で日射を適切にコントロールしたりといった対策が有効です。土地の気候や日当たり、風向きを考慮した最適なプランを立てるには、高性能住宅の設計に精通した住宅会社や建築士に相談しましょう。
住宅会社により施工精度が左右される
高性能住宅は、高性能な建材を使用するだけでなく、設計上の理論値に基づき、いかに正確に、そして丁寧に施工するかといったことも問われます。例えば、断熱材の隙間や気密シートの破れなどわずかな施工不良でも、住宅全体の性能が大きく損なわれる可能性があるためです。どれだけ高品質な建材を使っても、施工が伴わなければ期待通りの性能は発揮されません。
そのため、高性能住宅を建てる際は、高い施工精度を維持できる技術力と、多くの実績を持った住宅会社に依頼することが、家づくり成功への第一歩といえます。
高性能住宅を選ぶ際のポイント

後悔のない家づくりを実現するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、高性能住宅を選ぶ際にぜひ確認していただきたい項目を詳しく紹介します。
自身にとって重要な性能項目を明確にする
高性能住宅といっても、どこに重点を置くかは人それぞれです。
例えば、家族にアレルギー体質の方がいれば空気の質や結露対策を重視するでしょうし、光熱費を徹底的に抑えたいなら省エネ性や断熱性を最優先するかもしれません。また、地震への備えを一番に考える方もいるでしょう。
まずは家族で話し合い、自分たちのライフスタイルや将来設計、そして住まいに対する価値観を明確にすることが大切です。どの性能項目が自分たちにとって最も重要なのか、優先順位を整理しておけば、住宅会社との打ち合わせもスムーズに進み、本当に必要な性能を備えた家づくりにつながります。予算も考慮しながら、バランスの取れた選択をしていきましょう。
性能表示や計算書を確認する
高性能住宅は明確な基準や定義がなく、住宅会社によってその構造や仕様はさまざまです。だからこそ、住宅の性能を把握する際は、必ず客観的な指標や公的な証明書を確認しましょう。
代表的なものが「住宅性能評価書」です。これは第三者機関が断熱性(UA値)や気密性(C値)、耐震等級、省エネ性能など多岐にわたる項目を評価し、等級や数値で示すものです。
また、省エネ性能に特化した評価として「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」があります。BELSは一次エネルギー消費量等級を星の数や数値で示し、省エネ性がひと目で分かる仕組みです。
これらの評価書や証明書を取得しているか、そしてその数値や等級の内容を必ず書面で確認しましょう。口頭での説明だけではなく、書類で裏付けを取ることで、後々のトラブルを防ぎ、安心して家づくりを進められます。
気密測定を実施しているか確認する
気密測定とは、住宅がどれだけ隙間なく施工されているかを専用の機器で測る作業のこと。この測定をきちんと行っている住宅会社は、施工の品質や気密性能に自信がある証拠です。実際に気密測定をすれば、設計通りの性能が出ているか数値で確認でき、もし基準に達していなければ、きちんと直してもらえるので安心です。
気密性は断熱性や省エネ性にも直接関わるとても稚拙な要素です。そのため、気密測定を標準で行っている会社なら、安心して高性能住宅づくりを任せられるでしょう。これは、信頼できるパートナーを選ぶ上での大切なポイントです。
▶サラホームでは気密測定の様子をYouTube動画で公開中!
【サクッと解説/気密測定編】今どき家づくりの基礎知識を設計士が解説!~C値から測定方法まで分かる気密測定動画公開~
施工事例や体験談を参考にする
高性能住宅の品質や住み心地は、実際に建てられた家を見たり、住んでいる人の話を聞いたりするのが一番です。複数の施工事例を見れば、その住宅会社の技術力や得意な仕様、実際の仕上がりまで細かく確認できます。
また入居者の体験談からは、住んでみて感じる快適さ、光熱費の変化、メンテナンスのしやすさなど、カタログや説明だけではわからないリアルな情報が得られます。見学会やオーナー宅訪問を積極的に活用し、さまざまな事例・体験談を比較検討することが、納得の家づくりにつながります。
信頼できる住宅会社の選び方
高性能住宅の成功は、結局のところ信頼できる住宅会社選びにかかっています。
まず、その会社が断熱・気密・換気といった分野で十分な知識と実績を持っているかを確認しましょう。過去の施工事例や、関連する有資格者がいるかどうかも大切な判断材料です。
また、家づくりでは密なコミュニケーションと、あなたの要望に対する的確な提案力も求められます。完成見学会やモデルハウスに足を運び、実際の住み心地や対応力を肌で感じるのもおすすめです。
加えて、引き渡し後のアフターサポートや保証体制の確認も忘れずに。長く安心してお付き合いできる、そんなパートナーを選びましょう。
まとめ|厚木・海老名・町田で高性能住宅を建てるなら「サラホーム」桜建築事務所へ

高性能住宅は、断熱性・気密性・耐震性・耐久性・省エネ性という5つの重要な要素をバランスよく備えることで、家族の健康・快適・安心・経済性を実現する住まいです。
温度差の少ない室内環境や災害に強い構造、長く住み続けられる耐久性、光熱費の削減など、日々の暮らしの質を大きく向上させるだけでなく、将来的な資産価値の維持にもつながるのが特徴です。
「サラホーム」桜建築事務所では、高性能住宅の考え方を徹底し、「美しく・健康・経済的・頑丈・長持ち」という5つの基準と、温熱環境・耐震性能・耐久性の3つのバランスにこだわった家づくりを行っています。
UA値0.46前後の高断熱、最高ランクの耐震等級3、結露や劣化を抑え長寿命を実現するスーパーウォール工法など、最新技術と厳しい品質管理で、ご家族が安心して長く快適に暮らせる住まいをご提案します。
サラホームの高性能住宅で、安心・快適な暮らしを始めませんか?モデルハウス見学や個別相談も随時受付中です。ぜひ一度、サラホームの家づくりをご体感ください。
▶サラホームの「構造・性能・保証」についてはこちら
――――――
監修者:髙橋 康征(たかはし やすゆき)
一級建築士/一級土木施工管理技士/CASBEE建築・戸建評価員/インテリアコーディネーター

日本大学生産工学研究科建築工学専攻修士課程を修了し、一級建築士として数多くのプロジェクトを手掛ける。家業の土木建設会社にて宅地造成・エクステリア施工業務を経て、桜建築事務所に入社。住宅分野に限らない幅広い知識による提案や固定観念に囚われない設計が好評を得ている。「ジャーブネット全国住宅デザインコンテスト グランプリ受賞」「2013年2022年2023年2024年LIXIL全国メンバーズコンテスト 地域最優秀賞受賞」など、住宅デザインコンテスト受賞実績を多数保有。